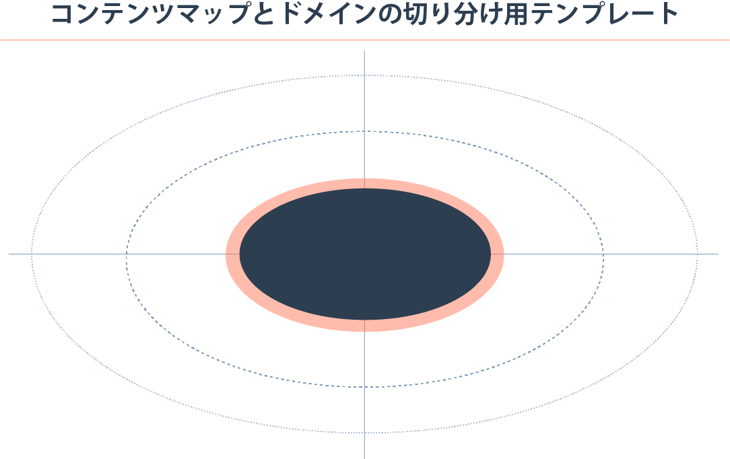最近、コンテンツマーケティングに取り組む企業は増える一方です。しかし、いろいろな企業のマーケターの方と話すと、コンテンツ制作に力を入れているものの思うような成果があがらないという悩みを持っている人が少なくありません。
その成果とは、コンバージョンやMQLの創出など、ずばり収益への貢献です。コンテンツマーケティングが収益拡大につながることが世に知られるなか、おそらく社内でのマーケティング部門へのプレッシャーも高くなっているのでしょう。
米国のWordPressVIP が最近リリースした「Content Matters 2023 レポート」でも、マーケターの 82% が「コンテンツを収益の原動力として使用することの重要性」が高まっていると述べており、優先順位も前年の5位から2位に上昇しています。
コンテンツマーケティングが収益につながらない要因として、最近よく見かけるのは「コンテンツをランダムに作り続けているパターン」です。品質自体は全体的に向上していると感じます。
そこで、本記事ではコンテンツマーケティング成功に欠かせない「コンテンツマップ」の基本や作り方を、弊社のテンプレートを用いて解説します。
コンテンツマップとは
コンテンツマップとは、文字通り「自社のコンテンツの地図」です。
マーケティング領域でのコンテンツマップの明確な定義は存在しないのですが、こちらのHubSpotの定義がわかりやすいでしょう。

(出典:HubSpot)
和訳:コンテンツマップとは、適切なコンテンツを、適切な人に、適切なタイミングで提供するための計画です。コンテンツマップは、コンテンツを消費する人の特性やライフサイクルステージを考慮し、提供するコンテンツの種類によって、よりニーズに合ったものになるようにします。
コンテンツマップとサイトマップの違い
コンテンツマップと混同されることが多いのがサイトマップです。
サイトマップとは、主に検索エンジンがコンテンツの発見と理解をしやすくするために、Webサイト全体の構造を示したマップのこと。簡単にいえば、サイトの設計図や地図のようなものです。
SEOの内部対策の一部であり、適切なサイトマップを作成することで、検索エンジンのページ理解を促進し、インデックスまでの時間を短縮できます。つまり、サイトマップはSEO対策やWebサイトのコンテンツ設計を最適化するためのものです。
対してコンテンツマップは、カスタマージャーニーの全体を通して、どのタイミングで、どのコンテンツを届けるべきかを可視化したものであり、コンテンツマーケティング全体を強化します。
コンテンツマップを作ることがなぜ大切なのか
コンテンツマップとは、自社がどのようなコンテンツを、どのペルソナ向けに、どのように展開していくかという戦略を可視化するものだといえます。
コンテンツマーケティングは、何よりも全体の設計がしっかりしていなければなりません。コンテンツマップを作成すると以下のメリットが得られます。
コンテンツをバランスよく配置できる
たとえば、見込み客の「気付き」のステージのコンテンツのみ充実していて、「検討」ステージに必要なコンテンツが少ないと、サイト訪問者は多くてもコンバージョン率は低くなるかもしれません。要は決め手にかけるのです。
逆に、「検討」ステージのコンテンツ、たとえば事例コンテンツは用意しているけど、「気付き」ステージのコンテンツが少なければ、新たな見込み客層を流入させる力は弱まります。
筆者の感覚だと、多くのBtoB企業は後者のパターンが多いです。決定段階のコンテンツが大半であり、オウンドメディアの記事はPV数を指標としたビックワード狙いが中心です。
こうなると、決定段階のオーガニック流入の大半は既存のマーケティング施策でリーチできている人になり、「認知」ステージでは関連性が低い人の流入が増えます。
もちろんBtoBの鉄板コンテンツの事例から充実させるのは正解です。しかし、潜在層の見込み客のボリュームを増やすためには「認知」ステージも充実させる必要があります。コンテンツマップがあると、このようなコンテンツの偏りを防ぎ、バランスよくカスタマージャーニーに沿ってコンテンツを配置できます。
コンテンツの総合力でパワーを発揮
キラーコンテンツが単体でバズっても、それだけで見込み客は「よし、買おう」と決断するわけではありません。特にBtoBの場合、見込み客はさまざまな角度からベンダーやプロダクトをチェックします。
たとえば、最近の調査ではBtoB購入者の 72% が、社会的責任のある企業から購入する可能性が高いと述べています。信用度を高めるコンテンツは、今ならSDGs、コンプライアンス方針、あるいはこれまでの業績の推移、レビューサイトの評価などでしょう。
特に中小企業の場合、このようなコンテンツは最初に計画していないとついつい制作が後回しになりがちです。コンテンツマップがあることで、コンテンツの総合力を発揮できるようなコンテンツの配置を考えることができます。
コンバージョンレートを高める
適切な場所に適切なコンテンツがあれば、見込み客は離脱せずランディングページや問合せページにたどりつけます。また、問合せページ、ランディングページに到達したあと、多くの見込み客はそこで迷うものですが、そこで購入意欲を再度喚起させるようなコンテンツが配置されていると、問合せへのハードルが下がります。
- ケーススタディ
- レビューサイトの評価
- 導入実績の伸び具合
コンテンツマップにもとづき、しかるべき場所にキラーコンテンツを配置できると、コンバージョンレートのアップを促進します。
コンテンツマーケティングのROIを高める
現時点の、既存コンテンツのトピックをコンテンツマップにマッピングしてみましょう。
成果と照らし合わせて見ると、過剰になっているトピック、あきらかに欠落しているトピックに気づくかもしれません。一方、1割程度はキラーコンテンツがあるはずです。
コンテンツマップで既存コンテンツを整理することで、不要なコンテンツの作成を避け、、優先順位の高いコンテンツを作成したり、キラーコンテンツのトピックをアレンジして活用したりなど、コンテンツの配置を最適化できます。つまり、ROIを向上させられるのです。
(Content marketing institute、MarketingProfs)
コンテンツマップはどのようなときに作成するのか
それでは、どのようなときにコンテンツマップを作成するべきなのでしょうか。ここでは、コンテンツマップを作成するべき3つのタイミングをご紹介します。

コンテンツ戦略の初期段階
コンテンツマーケティングで重要なのは、当然ながら質の高いコンテンツを多く発信することです。
しかし、コンテンツ制作に時間をかける余裕がないという方は多いのではないでしょうか。2022年にサイトエンジン株式会社が実施した調査によれば、8割近くが更新頻度を上げられると思いながらも、半数以上が「時間がない」ことを理由として更新頻度が上げられないと回答しています。つまり、限られた時間の中で自社に必要なコンテンツのみを制作する必要があるわけです。

(出典:サイトエンジン株式会社)
十分な戦略を設計しないでコンテンツ制作をすすめた場合、次のような課題が発生しやすくなります。
- ターゲットの求める情報とズレてしまう
- 購買プロセスを適切にサポートできない
BtoBのSaaS企業が100本のブログ記事を公開したとしましょう。しかし、そのすべてが「課題認識フェーズ(認知)」向けのコンテンツだった場合、どうなるでしょうか。
ユーザーは最終的に比較・検討し、意思決定を行う必要がありますが、「ケーススタディ」「製品比較」「導入事例」といった購入フェーズを後押しするコンテンツがないため、集客だけできて、コンバージョンにつながらないという状況に陥ってしまうでしょう。
コンテンツマップを作成すると、「ターゲットの購買プロセス」と「必要なコンテンツの種類」を可視化できます。そのため、限られたリソースを有効活用し、認知から購買に至るまでのコンテンツ作成が行えるようになります。
既存コンテンツの棚卸しと最適化
コンテンツマーケティングを数年続けていると、ブログ記事、ホワイトペーパー、動画、メールマーケティング用コンテンツなど、気づけば数百、数千ものコンテンツが蓄積され、どれが有効でどれが不要なのか判断が難しくなることもあるでしょう。
この状態を放置すると、検索エンジンに重複コンテンツとみなされSEO評価が下がる、ターゲットのニーズが変化しているにもかかわらず古い情報を発信し続けてしまうといった問題が発生します。
こうした課題を解決するために役立つのが、コンテンツマップです。
コンテンツマップを用いることで、既存コンテンツを適切に整理し、最適化できます。整理した結果、たとえば認知フェーズ向けのコンテンツが多い一方で、比較フェーズ向けのコンテンツが不足していると判明するかもしれません。この場合、ホワイトペーパーや事例記事を新たに追加するアプローチの立案が可能です。
新規コンテンツの企画・制作時
コンテンツマーケティング成功の必要条件は、顧客にとって適切なタイミングで、最適な情報を届けることです。しかし、「どのフェーズにどのようなコンテンツが必要なのか?」を正しく把握しないまま新規コンテンツを制作すると、顧客の購買プロセスを進めるコンテンツを届けられません。
たとえば、「SEOコンテンツが多いから、ホワイトペーパーを作ろう」と思い立ち、社内のリソースを割いて作成したものの、実際にはリード獲得につながらず、ダウンロード数も伸びないといった状況に陥ることがあります。
この原因は、「そのホワイトペーパーがターゲットの購買プロセスのどこに位置するのか」を事前に明確にしていなかったことにあります。つまり、「誰に向けて、どのフェーズで、どんなコンテンツを作るべきか?」という設計が不十分だったのです。
新規コンテンツを企画・制作する際には、「コンテンツマップ」を活用し、ターゲットユーザーのニーズや購買プロセスに沿った計画的なコンテンツ制作を行うようにしましょう。
コンテンツマップ作成時にも役に立つ「トピッククラスター構造」
トピッククラスターとは、1つのピラーコンテンツ(中心記事)を軸に、関連するサブコンテンツ(クラスター記事)を展開する手法です。たとえば、「SEO」というピラーコンテンツと「内部SEO」「外部SEO」「SEOツール」といったサブコンテンツを内部リンクでつなげることで、各ページのSEO評価を高められます。

もともとはSEO手法として提唱されたトピッククラスターですが、これをコンテンツマップ作成にも応用できます。
どういうことかといえば、購買プロセスの各ステージを1つのトピックとみなし、各フェーズに必要なコンテンツをクラスター構造で整理して、ユーザーがスムーズに次のステップへ進めるよう設計するという考え方です。
BtoB向けデータ分析ツールのSaaSベンダーの例を見てみましょう。
.jpg?width=600&height=343&name=%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9(%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF).jpg)
このように、購買プロセスを中心に据え、各フェーズで求められる情報を整理することで、コンテンツが自然とトピッククラスター構造を形成します。
この方法を取り入れることで、ユーザーは自身の検討段階に合った情報をスムーズに見つけられるため、サイト全体の回遊率やコンバージョン率の向上につながります。また企業側にとっても、どのフェーズにどのようなコンテンツを充実させるべきかが明確になり、コンテンツの重複や不足を防ぎながら、より戦略的なコンテンツ制作が可能になるでしょう。
コンテンツマップのテンプレートを紹介
コンテンツマップのテンプレートは多種多様です。ペルソナが一人の場合、直線型のテンプレートでもよく、Excelでも作成できます。フォーマットに正解はありませんが、ここではExcel・Googleスプレッドシートと弊社がコンサルで使っているテンプレートを例として説明します。
Excel(エクセル)・スプレッドシートの場合
ExcelやGoogleスプレッドシートを使ってコンテンツマップを作成する際、一般的なフレームワークとして、縦軸に購買プロセスを設定し、横軸にターゲットペルソナや想定される課題、提供するコンテンツの種類を並べ、ユーザーの視点と企業の発信内容を対応づける構造を作ります。
たとえば、Googleスプレッドシートの列には以下のような項目を設定し、縦方向に各購買フェーズごとの情報を追加していきます。
|
購買プロセス |
ターゲットペルソナ |
ユーザーの主な疑問・課題 |
既存コンテンツURL or タイトル |
不足しているコンテンツ |
コンテンツ形式 |
優先度 |
メモ / CTA |
|
認知 |
マーケ担当者 |
「データ分析ってなに?」 「導入するとどんなメリットがある?」 |
SEOブログ記事 ホワイトペーパー「データ活用入門ガイド」 |
イラストや図解入りの初心者向け資料 簡単な費用対効果の事例紹介(概要) |
記事 資料 |
B |
CTA:問い合わせフォームへの誘導 |
|
興味・検討 |
現場のオペレーター |
「導入で現場の作業はどう変わる?」 「実際に成功している企業の事例が知りたい」 |
A社の事例インタビュー記事 |
部署ごとの活用ノウハウ 事例記事/動画 |
記事 動画 |
A |
CTA:無料デモ申し込みページへのリンク |
|
比較・評価 |
経営層 |
「競合ツールとの違いは?」 「導入時の投資対効果はどう算出すればよいのだろう?」 |
比較表「主要ツールの機能・価格一覧」 記事「データ分析にかかるコストの内訳」 |
詳細なROI試算テンプレート 他社ツールとの長期的費用比較(TCO)解説 |
記事 テンプレート |
A |
メモ:経営層用に、稟議を通しやすい具体的数値やグラフを強調 |
|
購入・導入 |
管理部門 |
「導入までのステップは?」 「社内稟議や承認フローをどう進めればよいのだろう?」 |
ブログ記事「導入ロードマップ:何をいつまでに準備する?」 マニュアルPDF |
社内稟議用のプレゼン資料 トラブルシューティングの動画マニュアル |
資料 動画 |
C |
CTA:導入支援の問い合わせ/サポート登録 |
|
継続・リピート |
導入済みユーザー |
「さらに高度な分析方法は?」 「新しい機能やアップデート情報を知りたい」 |
ブログ記事「高度な機能紹介:予測分析の活用」 既存ユーザー向けメルマガ |
アップデートごとの使用事例 ユーザーコミュニティでのQ&Aまとめ動画 |
記事 メール |
D |
CTA:アップセル(上位プランへの移行)案 |
このように整理すると、どの購買段階のユーザーに対して、どんな情報が不足しているのか可視化し、コンテンツ制作の優先順位を決めやすくなります。
まずは、購買プロセスごとに大枠を作り、ペルソナや課題、既存コンテンツ・不足コンテンツをリストアップするだけでも、全体像が明確になります。さらに、制作スケジュールや担当者情報も追加すれば、チーム全体で戦略的にコンテンツ制作を進められるでしょう。
LEAPTの場合
弊社では、複数のペルソナに向けたトピックを一目瞭然にできるように、円形のテンプレートを活用しています。このテンプレートではペルソナは最大4人まで設定し、それぞれの関心や課題に応じたコンテンツを配置できます。

上記画像の通り、円の構造は三層になっており、カスタマージャーニーの各ステージに対応させています。
- 外枠の円:「気付き」のフェーズ
- 中間の円:「認知」のフェーズ
- 最も内側の円:「検討」のフェーズ
また、円の中でペルソナごとの領域も決めます。たとえば、左上がペルソナA、左下がペルソナB、右上がペルソナC、右下がペルソナDのように配置することで、それぞれの特性に合わせたコンテンツを割り当てられます。これにより、どのターゲットにどの情報を届けるべきかが一目で把握可能です。
では、実際に福利厚生サービスを提供する企業向けに作成したコンテンツマップをもとに解説しましょう。

以下3名のペルソナを対象に、コンテンツマップにトピックを配置します。同じサービスの見込み客であっても、このようにペルソナは何タイプか存在します。
- 中小企業人事総務担当の森沢真紀子さん(左上)
- 大企業の人事担当の柏崎さん(左下)
- 中小企業の経営者三崎さん(右下)
気づき(外側の円)
このフェーズでは、各ペルソナが抱える潜在ニーズに気付く段階です。
たとえば、中小企業の人事・総務担当である森沢さん(左上)は、社内の雰囲気や従業員の不満、食生活、健康問題など、日々の業務の中で気になる点に関心を持っています。
一方、大企業の人事担当である柏崎さん(左下)は、離職率の改善や社内評価制度、人材育成、eNPS(従業員満足度の指標)、働き方改革といった組織全体のパフォーマンス向上に関わるテーマに興味を持っているのです。
中小企業の経営者である三崎さん(右下)は、就労支援や働く環境の整備、中小企業の採用戦略など、経営視点での課題解決を求めています。このように視座が変われば課題に思うことも違うため、最初に興味を持つトピックも異なります。そのため、外枠の円の気付きのステージには、ペルソナごとの「気付き」につながるであろうトピックを配置しましょう。
認知(真ん中の円)
認知ステージでは、ペルソナが自身の課題に対する解決策を求めて情報収集を始める段階です。
森沢さんは、従業員のエンゲージメントや満足度を向上させる方法、社内イベントの活用について調べるでしょう。
柏崎さんの場合は、健康経営やホワイト500の取得、採用ブランディングといった、大企業における人事戦略のヒントとなる情報に関心を持ちます。
三崎さんは、中小企業向けの福利厚生制度について詳しく知りたいと考えるかもしれません。この段階では、それぞれの関心に沿ったコンテンツを提供することで、自社のサービスを見つけてもらうきっかけを作ります。
検討(中央の円)
検討フェーズでは、ペルソナが具体的なサービスを比較し、どの企業のソリューションを導入すべきかを判断する段階に入ります。ここでは、企業名や製品名、サービス名、競合企業名、製品カテゴリー、競合製品名といった基本的な比較情報が重要です。
また、資料請求やセミナーへの参加、導入事例やユーザーの評価・評判など、実際の利用者の声を確認することも意思決定に影響を与えます。このようなトピックを中央の円に配置することで、検討フェーズの顧客にとって有益な情報を的確に提供できます。
ドメインの切り分け
弊社のテンプレートでは、コンテンツを展開するドメインごとに色分けし、どの情報をどのチャネルで発信するべきかを明確に整理しています。
- 白色の外側の円:外部メディア、オウンドメディアドメイン上でのトピック
- 黒い中央の円:公式のサービスサイト上のトピック
外部メディアやオウンドメディアとは、業界メディアや広告、各種SNS、プレスリリース、サブドメインの企業Blogなどです。潜在ニーズや課題を顕在化させる役割を持たせていることが多いので、外枠の円の気づきのステージ=オウンドメディアのトピックとしています。
中央の円は検討のステージ。事例やプロダクトの機能・特徴、企業情報についてのトピックが配置されています。このように切り分けると、主要トピックのどれをどのチャネルで展開するかを決める際にイメージしやすくなるでしょう。
コンテンツマップの作り方を具体例を用いて解説
ここでは、コンテンツマップの作り方を解説します。

ペルソナを作成
まず、ペルソナを作成します。ペルソナとは「半架空の顧客プロファイル」。どのような製品・サービスにも顧客の傾向があります。「うちのクライアントにはこんな業界、こんな企業規模、役職はマネージャー、こんな考え方の人が多い」と何となくはわかっているでしょう。このような特徴を詳細にペルソナシートにまとめて架空の人物を作ります。
方法としておすすめなのは、自社のロイヤル顧客のインタビュー、顧客アンケート、営業パーソンからのヒアリングなどをもとに特徴をピックアップすることです。CRMデータの傾向なども参考になります。
ペルソナ用テンプレートは、オンライン上にたくさん公開されています。紙、Excelやパワーポイント、Adobeのオンラインテンプレート、HubSpotのペルソナ生成ツールなど無料ツールも豊富なので、使いやすいものを選び以下のような項目をもりこみましょう。
名前もつけて、いかにも現実にいそうな人物にしてください。
- 仮名
- 年齢・性別・年収・個性
- 勤めている会社の業種・規模、役職
- 持っている予算
- 情報ソース(購読メディア、SNS、人脈)
- 仕事上の目標
- 仕事上のペイン(困っていること)
- 持っている予算、他
- キャリアのゴール
- 個性、価値観

(出典: 114534494 © Tatyana Merkusheva | Dreamstime.com)
カスタマージャーニーを作成
次に、カスタマージャーニーを作成します。カスタマージャーニーとは、前述のペルソナ(自社の架空のお客様)が、最初にニーズに気付いてから自社のサービスを見つけて、関心を深めて購入し、活用していく過程での心理・行動を可視化するツールです。
カスタマージャーニーマップのテンプレートもさまざまですが、弊社では以下のように直線型で「気付き」「認知」「検討」「購入」「利用」ステージにわけて、顧客の気持ちや課題、動きを追うスタイルにしています。
カスタマージャーニーを作成すると、ペルソナの気持ちや行動パターンが時間の経過とともにどう変化するかが可視化できます。いつどのようなコンテンツトピックで興味を惹きつけ、どのようなコンテンツでリードに転換してもらうかなど、コンテンツの流れをどう組み立てるべきかが見えてくるでしょう。
.png?width=535&height=264&name=%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88(%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB).png)
ペルソナごとのコンテンツトピックを作成
カスタマージャーニーにそって各ペルソナごとの「気付き、」「認知」「検討」のコンテンツのトピックを作成します。トピックを考えるときの情報源は、ペルソナ作成のときに行った顧客インタビューやアンケートなどの情報です。
Googleのサジェストももちろん参考にしますが、それだけだと他社と似たコンテンツ企画しか生まれません。顧客の声などをもとに作成したトピックだからこそ、自社のサービスを好む見込み客を惹きつけます。
トピックについては、慣れている方ならテンプレートにそのまま書き込んでもよいでしょう。初心者マーケターや、チームでコンテンツマーケティングを行っている場合は、みなでトピックのアイデアをどんどん書いていきます。最初はできる限りリストアップして、その上で取捨選択して主要トピックを選ぶとよいでしょう。
主要トピックが決まれば、あとあと関連コンテンツを増やすことは比較的簡単なので、ここでは中心的なトピックを決めれば大丈夫です。
ペルソナごとのコンテンツトピックをジャーニーに沿って配置
最後に、ペルソナごとのトピックをテンプレートのそれぞれの「気付き」「認知」の領域に配置します。
弊社の場合は、以下のように円形のテンプレートにマッピングしますが、1名のペルソナの場合は直線型のコンテンツマップにマッピングしてもよいでしょう。

すべてマッピングすると、各ペルソナのカスタマージャーニー上に途切れなくコンテンツトピックが配置できているかが判明します。もし1フェーズのコンテンツのみにトピックが集中している場合は、他のフェーズのコンテンツトピックを再考して増やしましょう。
意外に忘れられがちなのは、検討ステージにおけるDMU(バイイングセンター)向けのトピックです。BtoBでは稟議を上申すると役員、経営層ほか複数の購買関係者たちがチェックをします。「評判」「IR情報」などのトピックを入れておく必要があります。
現場が強い会社なら、「サポート」「FAQ」などのトピックも信頼性を高めるでしょう。
最近の英Inbox Insight社の「ABMのマーケティング調査レポート」では、コンバージョンを妨げる主な要因としてのひとつに「DMUのメンバー全員を織り込むことを怠った」ことをがあげられています。エンタープライズ向けのサービスは特に、ここで企業の信頼度を上げるコンテンツトピックを忘れないようにしましょう。
定期的にコンテンツマップの改善を行う
コンテンツマップを一度決定したらその方針でコンテンツ制作に入りますが、3カ月に1度ペースでミーティングを行って、みなでコンテンツマップを見直し、常に最適化し続けることが大切です。
社会の情勢が変わったり、革新的テクノロジーが登場したりするとペルソナの知りたい情報や課題は変化するからです。たとえば、今ならChatGPTの影響などに関心を持つ見込み客が増えているかもしれません。また、マーケティングチームのメンバーの顧客理解が深まることで、新たなトピックを見つけることもよくあります。
一生懸命練ったコンテンツマップのトピックが外れることもあります。キラーコンテンツなど1割程度です。しかし、シナリオにのっとってコンテンツを作り、常にコンテンツマップを進化させていけばコンテンツマーケティングの成果は上がっていきます。
コンテンツマップとCMSを連動させるには?戦略的コンテンツ管理の実践方法
コンテンツマップとCMSを連携させることで、コンテンツマップの管理運用を効率化できます。以下では、コンテンツ管理の3つの方法をご紹介します。
コンテンツマップをデジタルツールで可視化し、運用しやすくする
紙の資料やExcelでコンテンツマップを作成した場合、実際の運用で活用しにくくなります。
想像してみてください。
毎月10本以上のコンテンツを手動で記録するのは、意外と時間のかかる業務ではないでしょうか。また、「一度更新を後回しにしてから、ずっと更新されない」「類似コンテンツを作成してしまっていた……」というケースも考えられます。
そこでおすすめなのが、GoogleスプレッドシートやNotionなどのデジタルツールの活用です。デジタルツールを導入しても基本的には手動更新が必要ですが、情報の整理や検索、更新のしやすさが格段に向上します。
たとえば、GoogleスプレッドシートやNotionで管理すれば、フィルター機能や条件付き書式を使って条件に合致したコンテンツを簡単に抽出できます。また、共同編集機能を活用することで、複数のメンバーがリアルタイムで更新でき、情報の属人化を防ぐことが可能です。

(Notionでの作成例)
また、MiroやFigmaといったビジュアルツールを使えば、コンテンツフローを視覚的に整理できます。どのコンテンツがどのページとつながり、ユーザーがどのような流れで情報を取得していくのかを明確にすることで、サイト全体の導線設計が最適化されます。
特に、異なるフェーズのコンテンツ同士をつなぐリンク戦略や、CTAの配置を視覚的に確認できるため、マーケティングチームやデザインチームとの認識のズレをなくすのにも有効です。
タグやカテゴリを活用してCMS側で整理
コンテンツマップを手動で管理せざるを得ない場合、CMSの「タグ」「カテゴリ」「カスタムフィールド」を活用して管理するという方法が考えられます。
こうすることで、CMS上でコンテンツのフェーズやターゲットごとの分類をし、検索や整理がしやすくなるため、別途コンテンツマップを作成・管理する必要がなくなります。つまり、コンテンツマップを別途作成・管理するのではなく、CMSのタグやカテゴリ機能を活用してコンテンツマップの役割を果たすわけです。
実際にCMSで管理する際には、次のような設定を行うことで、コンテンツを適切に整理できます。
- カテゴリ(コンテンツタイプ別):「記事」「ホワイトペーパー」「ウェビナー」「ケーススタディ」
- カスタムフィールド(ターゲット別):「マーケティング担当者」「経営者」「営業担当者」「IT管理者」
タグで「認知」や「興味関心」といった分類をすることも可能ですが、タグは顧客がコンテンツを探すためのものです。ユーザー体験の低下を招く恐れがあるため、タグは「BtoBマーケティング」や「SEO」といった具合にコンテンツのジャンルで分類するとよいでしょう。
API連携やプラグインを活用し、コンテンツマップとCMSを自動同期させる
WordPressやHubSpotなどの拡張性の高いCMSを使用しているのなら、API連携やプラグインを活用して、コンテンツマップとCMSを連携して運用管理を自動化するのもよいでしょう。
たとえば、GoogleスプレッドシートとWordPressを連携し、スプレッドシートに新しいコンテンツを追加すると同時に、WordPress上に自動で下書きを作成する。NotionとHubSpotを連携して、Notion上のコンテンツマップを更新したら、HubSpotのブログ記事リストも自動で更新されるように設定するといった具合です。
連携にはある程度の技術力が必要ですが、高頻度でコンテンツを更新する場合、業務効率化の大幅な向上を見込めます。
コンテンツマップを効率的に作成できるツール
ここでは、コンテンツマップの作成に役立つツールを4つご紹介します。
表計算ソフト・文書作成ソフト
先ほどご紹介しましたが、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフト、Googleドキュメントをはじめとした文書作成ソフトは、初めてのコンテンツマップ作成におすすめです。
特に表計算ソフトは、大量のコンテンツ管理に適しており、「コンテンツタイトル」「ペルソナ」「カスタマージャーニーのフェーズ」などを指定することで、CMSへのコンテンツ登録やマーケティング施策との紐づけがしやすくなります。
表計算ソフトは複数人でのリアルタイムでの編集が可能、かつリンクだけで簡単に共有できるというメリットもあります。また、データのフィルタリングやソート機能を活用すれば、瞬時に「作成中」や「公開済み」、「認知」などのコンテンツを確認できます。
MA・CMS

(出典:HubSpot)
MAツールやCMSツールもコンテンツマップの作成におすすめです。なかでもHubSpotのMarketing Hubは、CMSと連携したマーケティング業務効率化ツールであり、コンテンツマップと直接連携しながら記事の投稿・管理・分析を行えるため、効率的な運用が可能になります。
さらに、HubSpot Marketing HubまたはCMS HubのProfessionalプラン以上では、トピッククラスター構築機能を活用できます。SEOで上位表示を狙いたいミドル・ビッグキーワードを入力すれば、HubSpotが自動でサブトピックキーワードの提案をする機能です。キーワード選定というSEO対策で重要ながらも、時間のかかる作業を大幅に効率化できるでしょう。
そのほか、HubSpot上でコンテンツの作成から公開まで行える、レポート機能、コンテンツの承認機能などコンテンツマーケティングを強化する機能が豊富に備わっています。
コラボレーションプラットフォーム
コラボレーションプラットフォームとは、メンバーが共同作業を円滑に進めるためのデジタルツールです。
Miro は、オンラインホワイトボードツールとして、チームでのブレインストーミングやワークフローの可視化などを支援します。コンテンツマップを作成する際にも、ペルソナごとのコンテンツフローをビジュアル化し、各フェーズに適したコンテンツを直感的に配置することが可能です。

(出典:Miro)
上記画像は無料で使えるカスタマージャーニーのテンプレートですが、これをアレンジするだけで、カスタマージャーニーに沿ったコンテンツマップを作成できます。さらに、付箋のようにアイデアを追加しながら、チームでリアルタイムにコンテンツ戦略を立案することも可能です。
マーケティングやコンテンツ制作チームがリモートワークを採用している場合、コラボレーションプラットフォームを使うことで、全員が同じ情報を共有しながらコンテンツマップの構築運用を行えます。
マインドマップツール
マインドマップとは、思考やアイデアを視覚的に整理するためのツールです。テーマを中央に配置し、そこから放射状に関連する情報を枝分かれさせていくことで、アイデアを直感的に整理できます。この特性を活かせば、コンテンツマップやトピッククラスターの作成も容易に行えます。

(出典:Mindomo)
Mindomoは、マインドマップだけではなく、コンセプトマップ、アウトライン、ガントチャートまで作成できるツールです。コンテンツマップを作成する際にも、各ペルソナの課題や興味を中心に据えて、それぞれのフェーズに適したコンテンツをマッピングできます。
たとえば、「中小企業の人事担当者」を中心に設定し、「気付き」「認知」「比較・検討」「購入」といったカスタマージャーニーの各フェーズを枝分かれさせ、それぞれのフェーズごとに具体的なコンテンツを配置することで、全体像が直感的に理解しやすくなります。
共有機能を活用すれば、メンバーとリアルタイムで編集しながらコンテンツ戦略を検討することも可能です。
まとめ
コンテンツマップは、コンテンツマーケティング全体の設計図のようなものです。
コンテンツマップがあることで、ペルソナに向けて、カスタマージャーニーの「気付き」「認知」「検討」のそれぞれのフェーズでしっかりした方向性のもとコンテンツを作っていくことができます。
コンテンツマーケティングでは、キラーコンテンツだけあっても大きな成果につながりません。一見地味ながら重要なコンテンツのトピックも最初から計画して、しっかりしたシナリオをもとにコンテンツを配置することで全体的な成果が向上します。
まずは、今時点の既存コンテンツのトピックをコンテンツマップに配置して、カスタマージャーニーにそって配置できているかを確認してみましょう。必要なトピックが網羅されていない場合は付け加えます。そうすることでこれまで作り上げたコンテンツもより威力を発揮するでしょう。