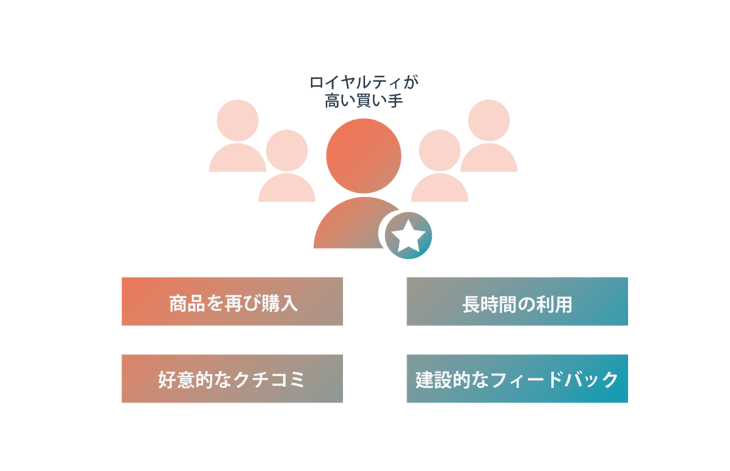一時期と比べあまり聞かなくなってしまったNPS®(ネットプロモータースコア)でしたが、SaaS企業やSaaSツール導入が広く普及してき始めているここ数年で、耳にする機会が増えてきたように感じます。
NPS®は2003年ごろからFred Reichheld(以下フレッド・ライクヘルド氏)によって広められた、調査相手が調査対象に対して、どのように感じているかを調査するときに利用される指標です。比較的新しい指標のため、「NPS®が何なのかよくわからない」という方も多いでしょう。そこで本記事では、以下の内容を詳しく解説します。
- NPS®と顧客満足度の違い
- NPS®の計算方法
- NPS®を扱う際の注意点
NPS®をどのように自社の事業の改善に役立てられるのか、具体的なイメージがつかめるようになるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
NPS®(ネットプロモータースコア)とは
NPS®(ネットプロモータースコア)は、調査対象のロイヤルティを測定する指標です。調査対象の一例としては、製品サービスの買い手が挙げられます。
これまで「買い手が企業やブランドに対して、どれほどの愛着や信頼感を持っているか」は測定が難しいと考えられていました。ところがNPS®を導入することで、ロイヤルティを具体的な数値として算出して、活用できるようになったのです。
しかも、NPS®を測る方法はとてもシンプルです。調査対象に対して「この企業(製品サービス、ブランド)を友人や同僚に勧める可能性はどれくらいありますか?」と質問して、その回答を集計するだけで、NPS®を算出できます。
この質問はシンプルではありますが、類似した数多くの質問との比較を繰り返す研究によって、ようやく発見されたものです。発見の過程は、フレッド・ライクヘルド氏の著書「顧客ロイヤルティを知る「究極の質問」」で、詳しく解説されています。
発展の背景

(引用元:https://www.nttcoms.com/service/nps/summary/ 動画を元に作成)
NPS®が多くの企業で活用され、発展した背景には、企業が買い手のロイヤルティを測定する必要性に迫られていた状況がありました。企業の収益の大部分は、ごく一部のロイヤルティが高い買い手によってもたらされる傾向があります。
そのため、企業にとってはロイヤルティが買い手を増やすことが重要課題であり、買い手のロイヤルティを把握する手段が求められていたのです。
これは、新規顧客獲得は重要なことながらも、新規顧客獲得よりも既存顧客から販売を拡大する方が、売り手の費用対効果が良いという観点からもいうことができます。だからこそ、ロイヤルティを正確に把握することは大切です。ロイヤルティが高い買い手には、一般的に以下の特徴があります。
- 商品を繰り返し購入する
- 企業との関係を長期間にわたって維持する
- 好意的な口コミを広げる
- 建設的な意見を企業に伝える
このように、ロイヤルティが高い買い手を増やすことは、収益面以外にも企業にさまざまなメリットをもたらします。だからこそ、多くの企業がNPS®に注目するようになったのです。
また、NPS®と混同されがちな指標に「eNPS(イーエヌピーエス)」があります。eNPS®は、従業員ロイヤルティを測定するための指標です。従業員に対して「あなたの職場の親しい知人や友人に勧める可能性はどれくらいありますか?」と質問して、その回答を集計して算出します。
NPS®(ネットプロモータースコア)がなぜ重要なのか?
ここまで述べたとおり、NPS®はSaaS企業を中心に注目を集めています。そのスコアはシンプルながら、顧客がブランドへ抱く感情を反映しており、NPS®を定期的に調査することで、自社のブランド力改善に寄与します。
しかし、NPS®を計測することがなぜ重要なのか、どのようなメリットがあるか、イメージが湧かない方も多いでしょう。ここでは、NPS®が重要である主な理由を4つ解説します。
顧客ロイヤルティの測定ができる
NPS®は、顧客が企業に対してどれほどの愛着や信頼感を持っているかを測定するための重要な指標です。シンプルな質問をすることで、顧客がその企業の製品やサービスにどれだけ満足しているかや、友人や家族に推薦する意向があるかどうかを数値化します。
顧客が高いスコアを付けることは、その企業に対する強い信頼と支持を意味し、すなわち顧客がブランドに対して持つポジティブな感情と、そのブランドへの長期的なコミットメントを示しています。
特に、高いNPS®スコアを持つ顧客は、繰り返し購入する傾向があり、企業との関係を長期間にわたって維持します。
Satmetrix社の「THE POWER BEHIND A SINGLE NUMBER」によると、航空業界の主要企業において、NPS®スコアと企業の売上高成長率に高い相関があることを示しています。

(出典:THE POWER BEHIND A SINGLE NUMBER)
さらに、企業の製品やサービスに対して好意的な口コミを広め、建設的なフィードバックを提供することが多いです。
これらの行動は、新規顧客の獲得、顧客満足度の向上に直結する上、結果的に企業の収益と成長に貢献します。
NPS®の変化から顧客の感じ方の変化を読み取れる
NPS®スコアの変化を追跡することで、企業は顧客の感じ方や態度の変化を時系列で捉えることが可能です。この分析は、顧客体験の改善や製品の質の向上など、ポジティブな変化を示唆する重要な手がかりを提供します。
逆に、NPS®スコアが低下している場合、対応品質の問題、製品の不具合、価格設定の誤りなど、顧客の不満や問題点が存在する可能性を示すため、企業は迅速な対応が求められます。このように、NPS®は企業が顧客満足度を継続的にモニタリングし、状況に応じて速やかに対策を講じるために有効です。
NPS®はシンプルながら、その数値の裏側にある顧客の感情を読み取ることが大切です。それによって、企業は顧客の期待を超えるサービスを実現し、顧客満足度の向上へとつなげることができるでしょう。
商品・サービスの改善につながる
NPS®を活用することで、企業は顧客からの具体的なフィードバックを収集し、製品やサービスの改善点を特定できます。たとえば、顧客が提供するフィードバックには次のようなものがあります。
- 製品の機能:〇〇機能の△△が便利
- 価格設定:〇〇機能は活用頻度が少ないので、金額が割高に感じる
- サービス品質:UIがわかりやすく、直感的に操作できる
- 顧客サポートの内容など:マニュアルがもう少しわかりやすいとよい
これらの情報をもとに改善策を実施することで、顧客の期待に応えることができ、顧客満足度の向上をもたらします。また、顧客からのポジティブなフィードバックは、企業が正しい方向に進んでいることを確認するための指標となり、チームのモチベーション向上にも寄与するでしょう。
また、NPS®は市場での競争優位性を確立するうえでも役立ちます。NPS®フィードバックを活用することで、顧客が最も価値を感じている製品の特徴やサービスを特定し、マーケティング戦略や販売戦略に反映させることが可能です。より顧客ニーズに即した製品・サービスを提供することができ、顧客満足度の向上を果たします。
カスタマーサクセスのフォローに役立つ
NPS®は、カスタマーサクセスチームが顧客との関係を強化し、顧客満足度を高めるためのアクションを計画するのに役立ちます。NPS®を利用することで、顧客が直面している問題を特定し、それに向けた対策を検討することが可能です。
特に、ディストラクター(低評価を与えた顧客)からのフィードバックは、問題の早期発見と解決のための重要な手がかりとなります。カスタマーサクセスチームは、これらの顧客に個別にフォローアップを行い、不満や懸念を解消することで、顧客満足度の向上とチャーン率(解約率)の低下を目指します。
また、プロモーター(高評価を与えた顧客)からのポジティブなフィードバックは、自社が提供する製品やサービスの強みを理解し、市場内での競争優位性の獲得やチームのモチベーション向上につながります。また、カスタマーサクセスチームは、顧客をブランドの代弁者として、口コミや事例紹介を通じて新規顧客の獲得を促進することも可能です。
NPS®(ネットプロモータースコア)と顧客満足度との違い
NPS®(ネットプロモータースコア)は「顧客満足度」と混同されがちですが、両者は別物です。そこでNPS®と顧客満足度の違いを3つ紹介します。きちんと使い分けたうえで、自社が調査対象からどのように評価されているのかを把握しましょう。
1.ロイヤルティを計測できるか
前述した通り、NPS®はロイヤルティを計測するために生み出された指標です。「この企業(製品サービス、ブランド)を友人や同僚に勧める可能性はどれくらいありますか?」という質問への回答を見れば、調査対象が自社にどれだけの愛着や信頼感を持っているかがわかります。
NPS®がロイヤルティを反映する要因としては、NPS®が「他人に勧める」という、ストレスの高い行動について聞いていることが挙げられます。友人や同僚に勧めることは、その人との関係性に悪影響を及ぼす危険がある行為です。
そのため、質問に回答する際には「その企業や製品サービス、ブランドは本当に信頼できるのか」と真剣に考える必要があります。自分の感情だけでなく客観的な視点からも考えることで、調査対象の心の奥底にある本音が現れて、ロイヤルティが反映されやすくなるのです。
その一方で「製品サービスに満足していますか?」と満足度を聞かれた場合は、自分の中だけで思考が完結しているため、深く考えずに回答しがちです。すると、とくに大きな不満がなければ、安易に「満足している」と回答しやすくなってしまいます。
実際に、顧客満足度はロイヤルティとの関連性が低いことも、フレッド・ライクヘルド氏の研究から判明しています。調査対象が製品サービスに満足していたとしても、愛着や信頼感を持っているかは、また別問題なのです。
2.業績との相関性
NPS®は顧客満足度と比べて、業績との相関性が高いことが知られています。業績との相関性が高い理由としては、NPS®が「心の満足」を反映していることが挙げられるでしょう。
人の満足には、理性による「頭の満足」と感情による「心の満足」の2つがあります。そして、調査対象が顧客満足度調査に回答する際には、この「頭の満足」のみが反映される傾向があるのです。
「頭の満足」では、「製品サービスが優れている」「価格が安い」といった点が評価されます。しかし、顧客満足度には「心の満足」が反映されにくいと考えられています。実際に「顧客満足度調査で「満足」と回答した人が直後に解約している」といったケースもあるようです。
一方で「心の満足」には、「自分を分かってくれている」「自分と価値観が合っている」などと、調査対象が企業に対して感じているかが反映されます。そして、こうした感情こそが、調査対象がリピート購入などの業績に直結する行動を取ってくれるかに、強く影響するのです。
NPS®には調査対象の「心の満足」が表れているからこそ、業績との高い相関性があります。だからこそNPS®は、業績を向上させるための指標として広く使われているのです。
3.グローバルな基準がある
NPS®にはグローバルな基準があるのに対して、顧客満足度にはありません。この点も大きな違いです。
NPS®では、フレッド・ライクヘルド氏が所属するベイン・アンド・カンパニー社の測定法が、標準的な基準となっています。各社が調査対象に対して同じ質問をして、同じようにNPS®を計算しているのです。そのため、NPS®は他社との比較が可能であり、自社の施策を考える際に役立てやすいという特徴があります。
一方で、顧客満足度は企業によってアンケートの設問や回答方法がバラバラであるため、回答結果を他社と比較しても意味がない場合が多いでしょう。業界内での自社の立ち位置を把握したい場合は、NPS®を算出して他社と比較するのが効果的です。
NPS®(ネットプロモータースコア)のマーケティングでの活用方法
NPS®は企業のマーケティング活動にも活用できます。実際に、NPS®は紹介マーケティングにも有効であることが明らかになっています。たとえば、「ROI of Customer Experience, 2020」では、顧客がある企業のサービスを「良い」と評価すると、その企業を推奨する可能性が38%も高まると述べています。
また、民泊オンラインプラットフォームを提供する「Airbnb」はNPS®を活用して、60 万人を超えるユーザーの今後の行動を予測しました。その結果、NPS®スコアが高い推奨者は、批判者に比べて再予約する可能性が13%高く、さらに友人を紹介する可能性が4%も高いことがわかりました。

(出典:Medium|AiAirbnb)

(出典:Medium|AiAirbnb)
このように、紹介マーケティングは、顧客からのポジティブな口コミを通じて新規顧客を獲得する戦略であり、NPS®はその効果を最大化するための鍵となります。企業は、顧客の事例研究、体験談、オンラインレビューを求めることで、紹介マーケティングの力を活用し、潜在的な新規顧客を引き付けることが可能です。
NPS®(ネットプロモータースコア)の種類
NPS®は、ロイヤルティと顧客満足度を測定するために用いられますが、その種類にはリレーションシップNPS®とトランザクションNPS®があります。それぞれ目的が異なるため、適切に使い分けることが大切です。ここでは、両者の違いを見ていきましょう。
リレーションシップNPS
リレーションシップNPSは、顧客と企業との長期的な関係に焦点を当てた測定方法です。この測定方法では、顧客が企業全体との関係をどのように感じているかを評価します。リレーションシップNPSは定期的(例:年に一度、四半期ごとなど)に実施されることが多く、時間経過による顧客ロイヤルティの変化を追跡するのに適しています。
たとえば、顧客が企業のブランド、製品、サービスに対して持つ全体的な印象や満足度を継続的に調査することで、顧客と企業を結ぶ関係性の強さを把握することが可能です。
トランザクションNPS
トランザクションNPSは、特定の取引や顧客体験の直後に実施される測定方法です。この測定方法では、顧客が特定の製品の購入、サービスの利用、またはカスタマーサポートとのやり取りなど、具体的なインタラクションに対してどのように反応したかを評価するために使用されます。
トランザクションNPSは、特定の取引や顧客体験が顧客満足度にどのように影響しているかを理解するのに役立ち、企業は具体的なフィードバックを得られます。
NPS®(ネットプロモータースコア)の計算方法
%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%96%B9%E6%B3%95.jpg?width=600&height=230&name=NPS%C2%AE(%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%82%A2)%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%96%B9%E6%B3%95.jpg)
(引用元:https://markitone.co.jp/column/importance-of-nps/)
世界標準となっているNPS®(ネットプロモータースコア)の計算方法を紹介します。まずは前述の通り、「この企業(製品サービス、ブランド)を友人や同僚に勧める可能性はどれくらいありますか?」と調査対象に質問します。その後の計算手順は以下の通りです。
- 調査対象に0〜10の11段階で評価してもらう
- 回答に応じて調査対象を分類する
- 0〜6は「批判者」
- 7と8は「中立者」
- 9と10は「推奨者」
- 推奨者の割合(%)から批判者の割合(%)を引く
- -100%〜100%の範囲で、NPS®(%)が算出される
NPS®は表計算ソフトなどで計算することも可能ですが、SurveyMonkeyなどのツールを利用することが一般的です。ツールのテンプレートを利用すれば、ほとんど手間をかけることなくアンケートを作成できます。あとは調査対象からの回答さえ集めれば、NPS®の計算はあっという間に完了するでしょう。
回答数を多く集めるほど、正確なNPS®を算出できます。大量の回答数を集めるのが難しい場合もあるでしょうが、NPS®の活用をあきらめる必要はありません。
NPS®の誤差の程度は統計学の手法で計算できて、約400のサンプル数があれば、誤差は5%以内に抑えられるとわかります。また、400人分の回答を集められない場合でも、100人分の回答があれば、おおまかなNPS®は把握可能です。誤差があることに留意すれば、回答数が少なくてもNPS®を活用できます。
NPS®(ネットプロモータースコア)の質問例
NPS®アンケートは、以下のような質問から構成されます。
<定量的フィードバック>
- 友人や同僚に私たちの会社を推薦する確率を0〜10の範囲で表してください。
- 私たちの(製品/サービス名)をあなたの知人に薦めることはありますか? 0〜10の範囲で評価してください。
- (会社名)を潜在的な就職先として、あなたの友人に薦める確率を0〜10で表してください。
<定性的フィードバック>
- 選んだスコアを決めた主な理由を教えていただけますか?
- 私たちが提供する体験をどのように改善すればよいと思いますか?
- あなたが最も価値を見出している製品/サービスの機能は何ですか? また、それはどの程度頻繁に使用していますか?
- 私たちの提供する体験において、不足している点や改善が必要だと感じたことはありますか?
- 私たちがあなたの幸福を向上させるためにできることは何だと思いますか?
これらの質問を通じて、企業は具体的な問題点や顧客体験を向上させる鍵を見つけることができます。定量的フィードバックは、0から10の評価の質問に対する回答から得られ、定性的フィードバックは、評価が提供された後のフォローアップの質問から得ることが可能です。
特にNPS®調査では、数値スコアに加えて、顧客がそのスコアを選んだ理由を尋ねるフォローアップ質問を含めることが一般的です。これにより、企業は顧客のフィードバックをより深く理解し、具体的な改善点を特定できます。
NPS®(ネットプロモータースコア)の注意点
NPS®(ネットプロモータースコア)は正しく扱わなければ、効果的に活用できなかったり、誤った判断につながってしまったりします。NPS®を扱う際の注意点を4つ紹介するので、失敗を避けるためにお役立てください。
1. 日本人の回答は中心付近に寄りがち

(自作したイメージ図です)
日本人のNPS®は低くなりがちであることが知られています。その最大の原因は、日本人はアンケートに回答する際に、中心付近の数字を選ぶ傾向があることです。
つまり、日本人は0〜10の選択肢があった場合、「4、5、6」を選ぶ人が多いのです。勧める可能性についての質問でこれらを選んだ人は、前述の通り「批判者」に分類されるため、割合が高いとNPS®は低くなります。
NPS®を他社と比較する際には、海外企業のNPS®と単純に比較することは避けた方がよいでしょう。比較対象には、日本の同業他社を選ぶべきです。
2. 他社や他業種との比較をしすぎない
NPS®は時系列での比較を重視しましょう。NPS®は他社と比較可能な指標であるとはいえ、単純な比較が難しいケースも多いからです。前述した日本人の傾向も、比較を難しくする要因のひとつです。
NPS®は業界や業種によって傾向に大きな差があることが知られています。下図は、アメリカ企業の業界ごとのNPS®を調査した結果です。

(引用:https://www.netpromoter.com/compare/)
上図から、業界ごとのNPS®をいくつかピックアップして紹介します。
- デパート、専門店:58%
- ホテル:39%
- 健康保険:18%
- インターネットサービス:2%
このように大きな差があるため、異なる業界・業種の企業どうしの比較は避けるべきです。同じ業界・業種の企業であっても、NPS®は以下のような要因に影響を受けます。
- 調査対象にアンケートに回答してもらうタイミング
- 対面での回答かインターネットでの回答か
- アンケートの回答率
こうした要因の影響があるため、NPS®を他社と比較することには限界があるのです。しかし自社内であれば、こうした要因をある程度はコントロールできますし、調査対象がアンケートに回答した際の状況を詳しく把握できます。
そのため自社のNPS®こそが、最も有効に使えるデータだといえます。まずは他社との比較ではなく、自社内での時系列の比較でNPS®を活用するとよいでしょう。
3. アンケートの設問数を少なくする
調査対象に回答してもらうアンケートは、設問数を少なくしましょう。アンケートを作成すると「せっかく回答してもらうのだから」と、あれこれ設問を増やしたくなるものです。しかし、設問を増やしすぎると、以下のようなデメリットが生じます。
- 回答者の負担になる
- 気にする指標が増えてNPS®が軽視される
- 改善施策の方針を決めにくくなる
また前提として、NPS®を算出するためのアンケートでは「この企業(製品サービス、ブランド)を友人や同僚に勧める可能性はどれくらいありますか?」という質問を最初に設置しましょう。他の質問項目の影響をできるだけ取り除くためです。
たとえば「受付の店員の対応に満足しましたか?」という質問が直前にあると、調査対象は受付の店員をイメージしながら「勧める可能性」についての質問にも回答してしまう傾向があります。アンケートでは最初に「勧める可能性」について尋ねたうえで、その後の設問数は絞るように気をつけましょう。
4. 回答しなかった調査対象のことも考慮する
NPS®を算出する際には、アンケートに回答しなかった調査対象のことも考慮しましょう。NPS®はあくまでも、アンケートに回答した調査対象からの評価のみを対象にして、算出されるものだからです。
アンケートに回答する調査対象は、製品サービスに満足している場合が多い傾向があります。製品サービスに不満を持った顧客は、わざわざ企業のためのアンケートに時間を使わないことが多いからです。
つまり、NPS®は実情よりも良いスコアになりやすい傾向があるといえます。アンケートへの回答率が低いほど、製品サービスに満足した人が回答者に占める割合が増えるため、この傾向が顕著になりがちです。
正確なNPS®を測定するためにも、アンケートの回答率を上げる努力をすべきです。そして、アンケートの回答率を100%にすることは現実的に難しいので、アンケートに回答しなかった調査対象がいることを、つねに忘れてはいけません。
5. 回答後にフォローをしてもよいかの許可も得る
NPS®調査を実施する際には、アンケート回答者に対して、必要に応じてフォローアップを実施してもよいか尋ねることが重要です。なぜなら、すべての顧客が自分の問題をすぐに解決して欲しいと考えているわけではないからです。
また、アンケートの配布方法によっては、顧客の連絡先情報(電子メールや電話番号など)が既に分かっている場合とそうでない場合があります。連絡先情報が分かっていない場合には、フォローアップの許可を得ると同時に、連絡先情報を尋ねることが推奨されます。
具体的には、「NPS®でお客様の状況をすべて把握することは難しいため、ご回答頂いた内容によって詳細のヒアリングにご協力いただけますか」といったように、許可を取りましょう。タイミングとしては、アンケート回答前に行うことが推奨されます。
なぜなら、人によってフォローアップを受けたくないと感じる方もいるため、その方にお願いしてしまうと顧客満足度の低下や、断られることで企業側に非効率も生じてしまうためです。
NPS®(ネットプロモータースコア)の利用シーン
NPS®(ネットプロモータースコア)とアンケートの他の質問項目を組み合わせることで、調査対象からのより詳細なフィードバックを得ることが可能です。NPS®とフィードバックの具体的な利用シーンを3つ紹介します。
1.製品へのフィードバック
製品を利用してもらう以外に調査対象との接点が少ない場合は、NPS®は「製品への満足度」とほぼ連動します。製品に満足さえすれば、調査対象は「友人や同僚にも勧めたい」と感じるからです。そうした製品の例としては、オンラインで購入された服や日用品が挙げられます。
この場合、NPS®を向上させるためには、調査対象からのフィードバックを元に製品を改善することが大切です。たとえば「シャツのボタンがすぐに外れてしまう」「外箱が開けにくい」といったフィードバックを受けたら、問題をできるだけ早期に解決しましょう。そうすることでNPS®が向上して、企業の業績も良くなると見込めます。
2.カスタマーサクセスへのフィードバック
カスタマーサクセスの実現度は、多くの場合でNPS®と強い相関性があります。他人に勧めるかを決めるうえで、製品サービスによって自分が期待した成果や成功を手に入れられたかが、大きな判断基準になるからです。
「期待した成果を得られなかった」という回答がアンケートで多かったのであれば、すぐに対策すべきです。具体的には、成果を得ようとした際に発生するであろう課題を予測して、その課題に先回りして解決しましょう。
たとえば、ソフトウェアのアップデートに手間取ることが予想されるのであれば、アップデートが必要になるタイミングで、わかりやすいマニュアルを作って送付すると効果的です。調査対象はアップデートをスムーズに済ませたうえで、ソフトウェアを使って成果を得ることに集中できます。結果としてカスタマーサクセスが実現し、NPS®が向上しやすくなるでしょう。
3.サポート体制に対するフィードバック
NPS®を向上させるためには、調査対象からのサポート体制に対するフィードバックに対応することも重要です。しっかりしたサポートが受けられない製品サービスでは「友人や同僚にも勧めたい」とは思えないからです。
とくにSaaSのように、アップデートなどによって操作方法の変更やトラブルが起こりやすいサービスでは、サポート体制の良し悪しがNPS®に直結します。そのため、調査対象にアンケートへの回答を求める際には、サポート体制へのフィードバックを積極的に集めましょう。
アンケートでは「サポートのどの部分に不満を感じたか」といった質問をして、選択式ではなく自由記述形式で回答してもらうと効果的です。すると、自社では想定していなかった不満を調査対象が持っていたことを、明らかにできる場合があります。そうした不満を解消できるようにサポート体制を見直すことで、NPS®と業績の向上につなげられるでしょう。
NPS®(ネットプロモータースコア)実行の手段
NPS®を効果的に実行するためには、顧客からのフィードバックを収集する適切な手段を選択することが重要です。主に、Web(ポップアップ)アンケート、メールアンケートの二つの方法があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
Web(ポップアップ)アンケート
Web(ポップアップ)アンケートは、Webサイト上にポップアップ形式のアンケートを表示させる方法です。顧客がWebサイトを訪問中にフィードバックを求めることで、リアルタイムでの意見収集が可能になります。
この手法の主なメリットは、顧客が自社のサービスを体験している最中にフィードバックを得られるため、そのタイミングでの正直な感想を反映しやすい点にあります。また、特定のページやアクションに応じてアンケートを表示させることもでき、より具体的なフィードバックを収集することが可能です。
代表的なWebポップアップアンケートツールの例として、「Asklayer」があります。Asklayerは、Webサイトに簡単に組み込めるポップアップアンケートツールで、カスタマイズ可能なデザインやリアルタイムでのフィードバック収集機能を提供します。これにより、訪問者の直接的な意見を効率的に収集し、Webサイトやサービスの改善に役立てることができます。

(出典:Asklayer)
メールアンケート
メールアンケートは顧客に直接メールを送り、アンケートに回答してもらう方法です。購入後やサービス利用後など、特定のタイミングで送ることで、顧客が体験を振り返りながら意見を提供できます。
メールアンケートのメリットは、顧客が自分のペースで回答できる点にあります。また、メールを通じて直接顧客にアプローチすることで、個々の顧客との関係を強化する機会にもなるでしょう。
代表的なツールの例として、「SurveyMonkey」があります。SurveyMonkeyは、メールを通じて簡単に配布できるアンケート作成ツールで、NPS®アンケートを含む多様な調査ニーズに対応しています。ユーザーは、SurveyMonkeyのプラットフォームを使用して、カスタマイズ可能なアンケートを作成し、顧客にメールで送信することができます。

(出典:SurveyMonkey )
まとめ
NPS®(ネットプロモータースコア)は、調査対象のロイヤルティを測定する指標です。顧客満足度とは異なり、業績との相関性が高いという特徴があります。NPS®にはグローバルな基準が存在するため、業界内での自社の立ち位置を探ることも可能です。
NPS®は「この企業(製品サービス、ブランド)を友人や同僚に勧める可能性はどれくらいありますか?」という質問への回答に基づいて算出されます。他のアンケート項目と組み合わせることで、自社の施策を考える際に役立てられるでしょう。本記事を参考にして、ぜひNPS®をご活用ください。